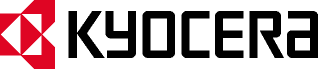PEOPLE
PEOPLE 03
デジタルトランスフォーメーション(DX)の実践 データ活用推進で新たな価値を創出する。 デジタルトランスフォーメーション(DX)の実践。データ活用推進で新たな価値を創出する。
DX推進本部 デジタル活用推進部
2020年入社
知能情報学部 知能情報学科卒
就職活動 入社動機
研究開発費や内部留保に注目した。
潤沢な資金をベースに研究開発に取り組める。
大学で専攻したのが画像処理分野です。その知見を活かすことを考え、就活では学部卒でも開発に携わることができる医療機器メーカーや、複合機メーカーを中心にアプローチしました。一方で重視していたのが、その企業の支出における研究開発費や資本における内部留保の割合です。これらの比率が高いことは、潤沢な資金をベースに研究開発に注力している証であると考えました。研究開発に携わりたいと考えていた私にとって、そこは重要なポイントでした。その観点から魅力を感じたのが京セラグループです。研究開発費および内部留保いずれもが高く、やりたいことがやれる場所と感じました。京セラグループ各社はいずれも魅力的でしたが、当社を選んだのはインターンシップの経験が大きかったと思います。研社員の皆さんの相互にコミュニケーションを取り合うフランクな雰囲気があり、それが自分のフィーリングと合っていると思い入社を決めました。
仕事内容 やりがい
クラウド上で
データ分析の仕組みを構築。
開発や生産の現場を
AI/IoT活用で支援する。
入社以来、DX推進本部でデジタル活用の新たな仕組みの構築に取り組んでいます。その一つが、データ活用環境の整備です。市場で稼働している当社の製品(複合機・プリンター)の印刷量やインク残量、紙詰まり、エラーなどのデータはシステムで全て把握できる環境にあります。しかしそれらデータは、今まで蓄積される一方で、有効に活用されていない現状がありました。私の取り組みは、クラウド上でこれらデータを分析する環境を構築することで、品質改善やマーケティングに活用していく仕組みを作ることです。もう一つは、開発現場や工場でのAI/IoTを活用した取り組みを支援するため、アイデアやサービスの効果検証を行うこと。たとえば、開発現場での図面チェックや工場での不良品検出などにおいてAIを活用する際、その最適化の検討などを進めています。これら取り組みは前例がなく、難しさがある反面、ゼロから自分たちの力で先進の新しいものを生み出すところに、大きなやりがいを感じています。
京セラドキュメントソリューションズで得た
入社後に身につけたシステム全体の知識を用いて、
AIの能力を最大化させる。
入社後、学生時代に触れる機会のなかったクラウドやデータベース・ネットワークなど、システム全体の「知識」を新たに吸収したと感じています。しかし当然ながら、これらは日々進化している世界ですので、今後もさまざまな機会を通じて知見を深めていきたいと考えています。AI/IoTで痛感しているのは、人の手によって入力されたデータの表記揺れの影響や生産現場に容易にセンサーデバイスを設置できないといった物理的課題など、理想論やあるべき論だけで解決できない課題が現実にあるということです。AIは万能ではなく、それを活用する我々のアイデアや工夫などが、AIの能力を最大化することを実感しています。また私の取り組みは、自分で考え自分で動く必要があります。入社以来、そのスタンスで業務に取り組んできましたから主体性が身に付き、「自走する意識」が強くなったと感じています。自分が走ることで周囲を巻き込み、DXを強力に推進していきたいと考えています。
5年後の目標/
もっと遠い未来の夢
「データドリブン」をけん引していく人材になり、
新たな価値創造に寄与したい。
5年後は、AI/IoT活用推進のスペシャリストに成長したいと考えています。AI/IoTの活用推進とは言い換えればデータを効果的に活用することであり、データの分析結果をもとに課題解決のための施策や経営の意思決定をサポートするなど、いわゆる「データドリブン」をけん引していく人材になりたいと思っています。もっと遠い未来の青写真も描いています。それは企業間の連携・協働を進めることで、新たな価値創造に寄与することです。たとえば、部品供給元が同一の会社や同じ課題を抱えた会社間で協力してデータ活用に取り組むなど、データやナレッジを共有する仕組みづくりを手がけたい。それが新しい価値創造のトリガーになると考えています。また京セラグループ内での協業にも期待しています。京セラは未来に向けて、スマートシティやスマートエナジーなど先進的なビジョンを描いています。グループ企業の一員として、それら取り組みにおけるデータ活用推進を担うなど、さまざまなプロジェクトにおいて、渦の中心になって周囲を巻き込んでいく存在でありたいと考えています。
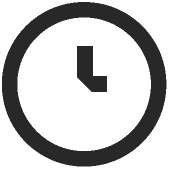
SCHEDULE
1日のスケジュール例
-
8:45
- 業務開始
- 在宅勤務時は自宅から会社のネットワークに接続し業務開始。メールチェックや定期ジョブに問題がないか確認。
-
9:00
- 打合せ
- 社内のデータ活用要件をヒアリング。
-
10:00
- パイプライン開発
- メンバーと協力して要件に応じたデータ定義や連携ジョブを作成。
-
12:00
- 昼食
-
13:00
- 打合せ
- 社内のAI/IoT活用要件をヒアリング。
-
14:00
- PoC(概念実証)
- クラウドサービスやプログラミングで要件に応じた業務改善が可能か実証を行う。
-
17:00
- 報告資料作成
- PoC(概念実証)結果を元に担当者への報告資料を作成。
-
17:30
- 業務終了
- 成果を振り返り日報を作成、翌日の準備を行い業務終了。
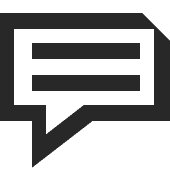
TOPICS
オフタイムの過ごし方
最近はオフタイムを同期と過ごすことが多くなりました。私の入社年度はコロナウイルスの影響を受け、入社式の中止や研修の延期により同期と繋がりが持ち難い状況でした。行動が制限された中では個人の趣味に没頭しがちでしたが、オンライン研修などで交流を持つ機会が増えたこともあり、今ではそれぞれの部門の課題や業務プロセスを共有したりしています。また、業務ではデスクワークが多いので、休日は体を動かすことも心がけています。